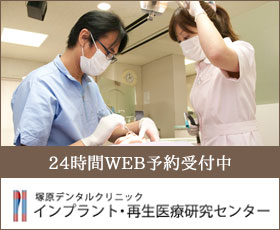発熱や頭痛など、「なんだか体調が優れない」と感じる時、もしかしたら唾液腺が炎症を起こしているのかもしれません。
しかし、唾液腺炎と聞いてもいまいちピンとこないという方も多いのではないでしょうか。今回は、唾液腺炎の症状・治療法など、あまり知られていない唾液腺炎の基礎知識についてご紹介します。
今後、万が一唾液腺炎になってしまった時に焦らず対応できるよう、是非ご参考にしてください。
Contents
唾液腺炎とは?
唾液は、唾液腺という臓器から分泌されます。唾液腺には大唾液腺と小唾液腺と区別されており、唾液の95%は大唾液から分泌されます。大唾液腺には耳の下にある「耳下腺」、顎の下にある「顎下腺」、舌の下にある「舌下腺」の3種類があり、この唾液腺に腫れや痛みを伴う炎症を起こしたものが唾液腺炎になります。
唾液腺炎には「化膿性唾液腺炎」と、「流行性耳下腺炎」の2種類あり、それぞれで特徴や治療法が異なります。
化膿性唾液腺炎
唾液の分泌量が低下した時に発生しやすい疾患で、口の中に常在する菌(主に黄色ブドウ菌・溶連菌・肺炎球菌)が唾液腺の開口部から侵入して発生するものです。
耳下腺炎
耳前部皮膚の腫れ、発赤、側頭部から顔面部への痛みの拡散といった症状が現れます。耳下腺部の圧迫によって、導管(唾液が出る管)開口部から排膿がみられます。
顎下腺炎
口底部または顎下部の腫れ、自発痛(なにもしていなくても起きる痛み)が現れます。口底部または顎下部の圧迫によって舌下部の導管開口部から排膿がみられます。
小唾液腺炎
口唇腺、口蓋腺、頬腺、舌腺などの小唾液腺に化膿性唾液腺炎が起こると、小唾液腺炎が存在する部位の口腔粘膜に腫れ、発赤、自発痛が現れます。
化膿性唾液腺炎は、慢性のものでは唾液腺が硬くなり、唾液の分泌が低下し口内の乾燥に繋がります。
化膿性唾液腺炎の治療方法
急性の化膿性唾液腺炎に対しては、殺菌性のうがい薬などで口の中の清潔を保つとともに、抗菌薬を投与します。
慢性の化膿性唾液腺炎の場合は、口の中の乾燥が酷い場合があります。その際は、うがい薬や人工唾液を使用することもあります。症状が悪化すると膿を出す手術が必要になることも。
口の中を清潔な状態で保つことが大切です。
流行性耳下腺炎
流行性耳下腺炎は、一般的には「おたふくかぜ」と言われることが多いですね。
おたふくウイルス(ムンプスウイルス)による伝染性疾患で、咳などの飛沫感染や、唾液などでの接触感染でうつります。感染力が非常に高く、家族や幼稚園、小学校など、子ども同士が密接に接触するところで流行ります。
小児、特に2~6歳児で感受性が高く、潜伏期間は2~3週間ほどです。
おたふくウイルスに感染すると、両側あるいは片側の耳下腺(耳たぶ~耳の前の顎のラインに沿った部位)が腫れてしまいます。通常は片側から腫れ、1~2日のうちにもう片方も腫れる場合が多いそうですが、稀に片側の腫れで済む方もいらっしゃるそうです。
発症から3~4日間は痛みが強く、唾液の分泌が促される時(酸っぱいものを食べる、唾液の分泌が多い朝など)にさらに痛みが増します。他にも発熱、頭痛、四肢の筋肉痛の症状が現れ、その後約7~10日で軽快しますが、髄膜炎や脳炎など、他の病気との合併に注意しましょう。
また、耳下腺をはじめ甲状腺、睾丸、卵巣、膵臓などの腺性臓器に臓器障害を起こす場合があり、稀に感音性難聴を合併します。多くは片側に症状がみられ、永続的な後遺症となり予後は不良です。
成人の流行性耳下腺炎は、小児よりも症状が重くなる傾向があります。
流行性耳下腺炎の治療法
流行性耳下腺炎では、全身では安静と解熱鎮痛剤の投与、局所的には冷湿布とうがいを行う場合が多いです。また、合併した病気によって治療は異なります。
髄膜炎を疑う症状がみられた場合は輸液療法のため数日間の入院が必要になることも。
事前の対策としては、おたふくかぜ弱毒生ワクチンという予防接種が有効です。
唾液腺炎の検査・診断方法
不調を感じて病院で受診した際、どのような検査をするのでしょうか。
- 腫れている部位が唾液腺であるか確認
- 血液検査
- 培養検査
- 超音波検査
- 頭部CT検査
- 頭部MRI検査
このような検査を行い、唾液腺炎であると診断します。
腫れている部位を確認する際は、他の器官と間違えられやすいので注意が必要です。ご自身で腫れている部位をチェックし、唾液腺炎ではないと独断で決めてしまうのは危険なので、必ず病院で検査を受けてください。
「唾液腺炎ではない、きっとただの風邪だから様子を見よう」と判断し、もし流行性耳下腺炎だった場合、合併症で死に至ることも考えられます。
医師による治療を受けることで、気が軽くなり、回復が早まる可能性もあります。
唾液腺炎は何科?
唾液腺炎の症状が起こった際に適した初診科は、歯科口腔外科、耳鼻咽喉科です。
発熱や頭痛の症状が引き起こされるため、風邪と間違えて内科に行く方が多いですが、他に今回ご紹介したような症状がみられた場合は、歯科口腔外科、耳鼻咽喉科をおすすめします。
また、化膿性唾液腺炎の原因である唾液の分泌量の低下は、虫歯や歯周病などの口内トラブルにも繋がります。歯科医院での検診も大切ですね。
まとめ
いかがでしたか?
唾液の分泌量の低下は、生活習慣の乱れ、ストレス、水分不足などから起こります。唾液腺炎の1番の予防は、ストレスを溜め込みすぎず、生活習慣を見直し、改善することでしょう。アルコールの摂取量を見直す、咀嚼回数を増やす、鼻呼吸などを意識してください。
また、唾液腺炎に限らず、「単なる風邪」だと思って放置していた結果、命の危機に関わる病気だった…ということは十分考えられることです。治療を受けるのが遅かったために後遺症が残ることもあります。
早期発見・早期治療を心掛け、しっかりと医師の指示に従いましょう。