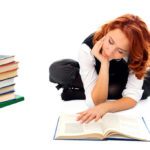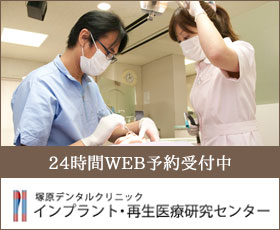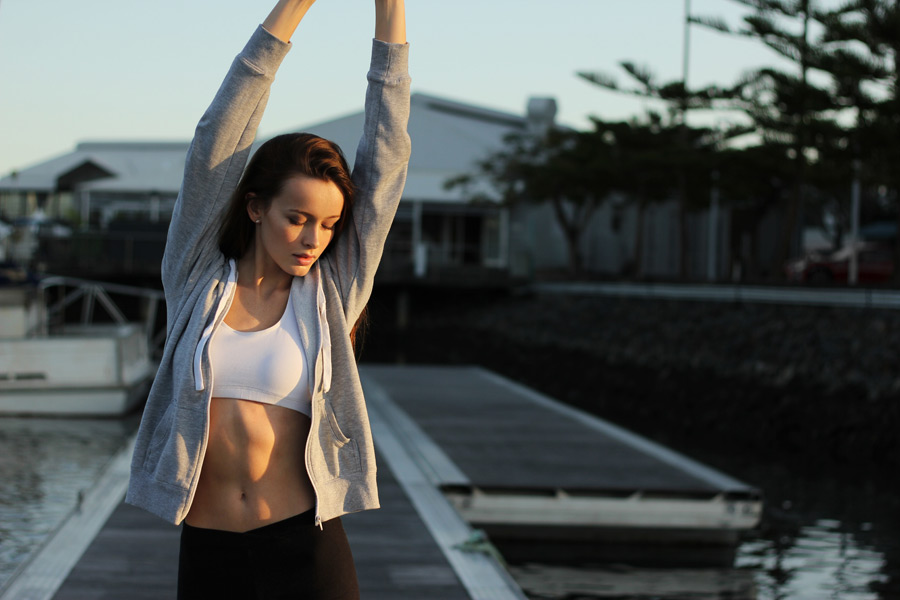
皆さんは何のために歯磨きを行っていますか?口の中を清潔に保ち、虫歯や歯周病、口臭などを予防するためという方が多いのではないでしょうか。
もちろん口の中を清潔に保つことは歯を守るために非常に重要なことなのですが、実は歯だけではなく全身の健康を守ることにも繋がっているということをご存知でしょうか。
最近の研究では歯周病が腸内環境を悪化させているという報告があるほど、腸と口内環境には密接な関わりが指摘されているのです。
食べ物は口から胃へ流れていき、その後小腸や大腸で栄養分を体内へと取り込み、肛門から排出されます。食べ物を飲み込む際には胃や腸に唾液が一緒に流れ込み、口の中に生息している細菌も一緒に胃や腸へと流れていきます。つまり体内に栄養や細菌を取り込むのは「口」が始まりということです。
今回は体内に栄養を摂り込む始まりとなる口内環境と、腸との関係に焦点を当ててお伝えします。口と腸になぜ関係があるのか疑問に思う方、歯周病が口の中だけの病気だと思っている方は必見です。
Contents
歯周病菌が腸内バランスを崩す
歯周ケアが行き届いていなかったり、糖分を多く摂取することで溜まっていく歯垢(プラーク)には、10億個もの細菌が存在し、歯周病の大きな原因となっています。
歯周病は多くの方がかかる恐れがある病気ですが、口腔内に悪影響を及ぼすだけでなく、腸内環境に影響を及ぼしていることが分かっています。
本来、腸内細菌の割合は、善玉菌が2割、悪玉菌が1割、日和見菌が7割というバランスが理想とされています。しかし、食生活の乱れやストレス、老化、抗生物質の服用などによる影響で腸内細菌のバランスが崩れてしまいます。すると悪玉菌が増加して、腸の調子が悪くなったり、糖尿病、高血圧、心臓病といった現代病に、かかりやすくなったりしてしまうのです。
腸内バランスが全身の健康を守るために重要であることは明確ですが、歯周病はそんな腸内バランスを崩してしまう原因のひとつになってしまうのです。
腸内環境と食生活
腸内環境と生活習慣病は密接な関係にあります。
不摂生な生活を送ることによって発症する生活習慣病は数多く存在し、現在は子どもの生活習慣病患者も増えてきています。
特に栄養のバランスの偏った食生活が続いている場合には、腸管の善玉菌は少なくなり、悪玉菌が多く繁殖します。
悪玉菌が多く繁殖することで、食べ物が腸内で腐敗してしまい、腸管のバランスが崩れ、そこからよくない代謝産物が生まれて、健康を損なわせてしまうことになります。
そして、栄養バランスの偏った食生活を続けると、歯周病、糖尿病などの生活習慣病になり、あるいは、食物アレルギー、花粉症、アトピー性皮膚炎、金属アレルギーなどのアレルギー症状を起こします。
歯周病を招く食生活と腸内環境の関係
歯周病が進行している方の特徴として、食生活が乱れているということが挙げられます。
本来1日3食、決められた時間によく噛んで食べることができれば歯周病が進行しにくいものです。しかしだらだら間食をしたり、深夜近くにご飯を食べていたりすると、細菌が増えやすく歯周病が悪化しやすくなります。
また、噛む回数が少ない早食いの傾向が強い方はしっかり噛むことができず、食べかすが口の中に残りやすくなります。そしてファーストフードなどの油っぽい食べ物を中心とした生活も、軟らかい食べ物が多いため噛む回数も少なく、奥歯に挟まりやすいため口の中に食べかすが残りやすくなり歯周病を引き起こす原因になります。
腸内環境も同様で、油の多い栄養バランスの偏った食生活は、悪玉菌のエサとなり腸内環境を悪化させてしまうことになります。
歯周病が進行すればするほど、腸内環境は悪化し、悪循環になってしまいます。食生活の面でも歯周病をしっかりと予防することが非常に重要となります。
歯周病菌が腸まで届く理由
歯周病菌が血管から体内へ侵入する
なぜ口の中の細菌が腸内環境にまで影響を及ぼすかというと、口の中の細菌は歯茎の血管から体内に侵入できるからです。
歯周病菌が口の中で大量に繁殖してしまうと、歯茎の血管から体内へと侵入し、心臓にまで達することも分かっています。そのため歯周病とは関係が無いように感じる心臓病とも深い関わりがあると言われているのです。
当然歯周病菌は全身の血管を通じて腸に侵入することができます。腸に侵入した歯周病菌は悪玉菌を活性化し、腸内環境を悪化させます。
また、歯周病菌は炎症性の物質を分泌し、歯茎の腫れや出血を起こします。この炎症性の物質は口内だけでなく全身にも影響を及ぼします。
腸に歯周病菌が侵入し炎症を起こすと免疫物質が減少し、悪玉菌を刺激します。このダブル攻撃によって、歯周病菌は腸内環境を悪化させてしまいます。
腸には全体の7割もの免疫物質を作る役割があるため、腸に細菌が侵入し炎症を起こせば免疫が低下して風邪を引きやすくなる可能性が高まります。
食べ物や唾液と一緒に体内へ
歯周病の原因菌のひとつに、ジンジバリス菌があげられます。ジンジバリス菌は酸素を嫌う菌で、歯と歯茎の間に入りこみやすく、取れにくい特徴がある厄介な菌です。
これが食事の際に食べ物や唾液と一緒に腸内に流れ込んでしまうと、血液中の内毒素を増加させ、さまざまな組織や臓器に流れ込み、炎症を引き起こしてしまうことになります。
「腸は第二の脳」とも言われているほど体の中でも重要な器官です。そんな重要な腸内環境が悪化すれば、全身に悪影響をもたらしてしまうことになります。
腸内環境のバランスを崩れると・・・
小腸では、消化酵素と食べ物が混じり合い、必要なものが体内へと吸収されます。この時に小腸では吸収されなかったものが大腸へと運ばれ分解され始めます。
大腸で分解される物質は酢酸・プロビオン酸・酪酸などの有機酸です。これらの有機酸は腸にとって良い作用をおこすのですが、逆に悪い作用を引き起こす尿素毒などの有機物質を作ってしまう可能性があるのです。この有害物質は腸内環境を悪化させ、全身の健康にも悪影響をもたらしてしまうことになります。
まとめ
「口」と「腸」は、一見すると全く関係が無いないように思えます。しかし口腔内の環境と腸内環境のどちらか一方が不調になれば、全身の健康にも悪影響が起こってしまうものなのだということがさまざまな研究で明らかになっています。
日頃から歯磨きなどのお口のケアと同時に、腸内環境も見直して、健康な生活を送りましょう。ただ単に歯を磨くのではなく、口の健康がいかに全身の健康に影響を与えるのかを考えながら歯磨きをすると良いかも知れませんね。