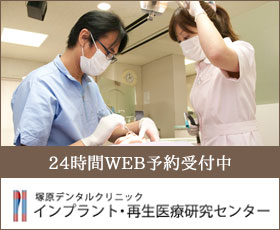今年は梅雨が長く、太陽の陽射しが待ち遠しかったのですが、梅雨明けした途端に蒸し暑く、連日の熱中症アラート!
私たちの身体もそれに対応していかないと体調を崩してしまいます。
野菜など農作物も日照時間が短かったため不作となり、値段が高かったり、店頭に並ばない物もありますよね。
太陽(紫外線)って悪者で、できる限りカットしたい!と思っている人も多いのではないでしょうか?
でも、実は私たちの健康にはとても大切なのす。
さらに今年はコロナウィルス問題の自粛で、仕事も家、お休みの日も家にこもっていることが多くなっています。
今回は太陽の恵みと今話題のビタミンDについてお話していきましょう。
こんな時期だからこそうまく付き合って健康な心身を手に入れましょう!
Contents
ビタミンDに働きは?
腸管でカルシウム、マグネシウム、リンなどの吸収促進をしたり、腎臓や副甲状腺でカルシウムのバランスを整えたりして、骨形成や骨の健康を保つ働きをしています。
また、最近注目されている作用として
ステロイドホルモンと同様に正常な細胞への分化を誘導したり(がんの抑制)
リンパ球などの免疫担当細胞の調整(リウマチ、Ⅰ型糖尿病など自己免疫疾患、アトピー性皮膚炎、喘息、花粉症などアレルギーに関与)
血圧上昇ホルモンの分泌調整などがあります。
なぜビタミンDが必要なの?不足するとどうなるの?
ビタミンDが不足すると小児ではくる病、大人では骨軟化症になってしまいます。
くる病では歩行が遅れたり、歩行時の疼痛、O脚、やX脚などの変形になることもあります。
また、骨軟化症は骨粗鬆症の一因となり、軽微な外傷でも骨折やすくなってしまいます。
女性にとって紫外線は、皮膚のエラスチンやコラーゲンを変性させしわやたるみの原因や日焼けによる色素沈着やシミの原因といった悪い印象が強いですよね!
美白のために、年間を通して日焼け止めクリームを欠かさなかったり、日傘、サングラス、手袋と完全防備をして紫外線をカットしている人も結構いらっしゃいます。
それと同時にお子様にも同じように紫外線を完全防護していたりします。
後で詳しく説明いたしますが、ビタミンDは日光に当たって活性化されはじめて働くようになります。
つまり紫外線をカットしてしまうとビタミンDは働かないのです。
最近では生まれたばかりの赤ちゃんがすでにくる病という報告も聞かれます。
ビタミンDを取るには?
ビタミンDを取るにはビタミンDを多く含む食べ物から摂取する方法と
皮膚にあるコレステロールを原料として、日光を浴びることで紫外線に作ってもらう方法があります。
ヒトにとって重要なビタミンDはビタミンD2とD3です。
ビタミンD2は植物性の食品(キノコ、海藻類)に含まれており、ビタミンD3は動物性の食品(魚、肝臓、鶏卵など)に含まれています。
ビタミンDは通常、強い生理活性を持たない前駆体(プレビタミンD)として存在します。そして肝臓や腎臓に運ばれ、活性型ビタミンDとなっていきます。
太陽とビタミンD
ヒトにとって最も大きなビタミンDの供給源は皮膚のコレステロールです。
皮膚に紫外線(UV-B)が当たることによって皮膚にある7-デヒドロコレステロール(プロビタミンD3)がプレビタミンD3になります。
その後、体温によってビタミンD3となり、タンパク質によって肝臓に運ばれ活性型ビタミンD3になります。
UV-Bはガラスや服、日焼け止めクリームなどを通過できません。
ステイホームでずっと家の中にいたり、日焼けを気にして日焼け止めクリームを塗っていることが多いとビタミンD不足になっている可能性があります。
特に冬はオゾン層に紫外線が吸収されてしまうため、皮膚に到達する紫外線量は少なくなってしまいます。(夏の1/4~1/5)
ビタミンDの多い食品
ビタミンDの多い食品に魚とキノコ類があります。
100g中に含まれる量では
キクラゲ(乾燥)(435~970μg)、しらす干し(61μg)、丸干し(50μg)、たたみいわし(50μg)、 鮭(35μg)、ウナギ(20μg)
干し椎茸(15μg)
これをみて気づきませんか?
ヒトだけでなく、お魚もキノコも天日干しにするとビタミンDが増えるのです!
椎茸はエルゴステリンと成分を豊富に含んでいますが、これは紫外線を浴びるとビタミンDに変化するので、
干し椎茸は生椎茸の2倍のビタミンDが含まれています。
ビタミンDと口腔
ビタミンDは小腸でのカルシウムやリンの吸収率を増加させ、新生骨や歯を作るのに欠かせません。
カルシウムとリンはハイドロキシアパタイト(骨の60%, 歯のエナメル質97%, 象牙質の70%)の結晶を作るのに必要で、
その血中濃度はビタミンDによって維持されます。
また、骨を丈夫にし、骨粗鬆症を予防します。
ビタミンDと健康
① 免疫力の強化
ビタミンDには細菌やウィルスを殺すカテリジンというタンパク質を作らせる働きがあります。
皮膚上にβーディフェンシンという抗菌ペプチドを作らせ、バリア機能を高める。
② アレルギー症状の改善
緩んだ腸粘膜の結合を改善し、適切な免疫抗体の産生を促します。
③ 脳や精神トラブルへの効果
脳内の神経細胞の保護や増殖、分化の調節
心や神経のバランスを整えるセロトニンを調節
うつ、統合失調症、自閉症、発達障害、認知症との関連
④ 糖尿病との関連
Ⅰ型、Ⅱ型とも発症リスクを軽減
⑤ がんとの関連
大腸がん、前立腺がん、乳がんの予後を改善
⑥ 妊娠の成立のと関連
妊娠しやすい身体作りを助ける(着床率、流産リスクの改善等)
⑦ 高齢者、フレイルとの関連
筋力低下、転倒との関連
まとめ
ビタミンDには様々な作用があり、私たちの健康に大きく関わっています。
植物性、動物性のビタミンDをしっかり摂取し、適切に紫外線を浴びて、免疫力の強い身体をつくりましょう!
ビタミンDの血中濃度が目標値で安定するための肝臓や脂肪内の備蓄には3ヶ月が必要と言われています。
確実に積極的に症状を改善したい時はサプリメントの使用が有効です